しかし、耳に入ってくるのはマイナスな情報ばかりなので『仮想通貨は何となく危険なものなのでは…?』と不安を抱いている方も少なくないでしょう。
実際に仮想通貨は手にとって使える法定通貨(円やドルなど)とは違い、インターネット上で取引をするため、目に見えないこともあり、その危険性や安全性について疑問視することも無理はないでしょう。
そこで今回は、「これから仮想通貨を初めてみたい!」と思っている方たちに、仮想通貨は本当に危険なのか?また、安全に取引をするためのポイントなどをご紹介したいと思います。
仮想通貨は本当に危険なの?
仮想通貨は良く耳にするけれども、取引をしたことがない人にとっては未知の世界ですよね。まずは仮想通貨の中で一番有名なビットコイン(BTC)を例として、説明させて頂きます。
ビットコイン(BTC)は価格変動が激しいという特性がありますが、逆にこの特性を利用して大きな利益を出すことも可能な仮想通貨です。
そのため、初心者にとってみればこのような価格変動にリスク(危険)を感じる事もありますが、人によってはメリットになる場合もありますので、一概にビットコイン(BTC)には危険性があるとは言い切れません。
また、仮想通貨の取引所では、ハッキングなどの取引における危険性を排除するために、様々なセキュリティ対策を行っています。
もちろん「100%絶対に安全!」と言い切れないところがあることは確かですが、それは、仮想通貨だけでなく株取引やFXなどの他の投資でも言えることでしょう。
そのため、仮想通貨の取引に関するリスクや危険性をしっかりと理解したうえで、取り組むことが重要になります。それでは、仮想通貨の考えられる危険性についてご紹介したいと思います。
株価よりも仮想通貨は価格変動が激しい
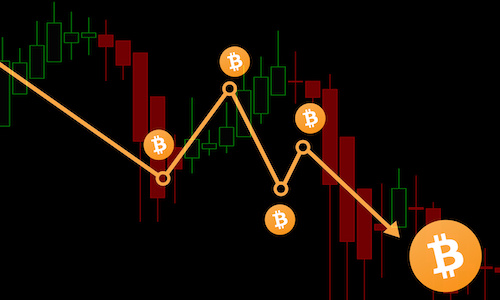
まず、株よりも仮想通貨の方が価格変動が激しいという特徴があります。ただし、大きな価格変動(乱高下)は株式市場でも同じことが起こります。
例えば、企業のトップの不祥事や法律違反などの問題が起こった場合に、株価は大きく下落します。逆に画期的なサービスがリリースされたり、業績の上方修正がなされたときなどは、連日大きく株価が上昇することもあります。
ただし、株式の場合は1日での株の上昇や下落など範囲が決まっているため、株価がその上限まで下落したら価格がストップする仕組みになっています。
しかし、仮想通貨は株価のように上昇や下落の範囲が決まっていないので、上がるときはとことん上がり、下がるときもどこまでの下がり続けてしまいます。これらが、仮想通貨が株価とは違う乱高下を引き起こす理由となります。
仮想通貨は株と違って企業が発行するものではなく、有価証券報告書などもないため、需要と供給のバランスによって価格が変動します。
仮想通貨は将来性を高く評価されていることもあってか、ここ数年で価値は高まってきていますが、世界的な様々な規制やトラブルなどによって、仮想通貨の価値が急激に下がったりすることもあります。
このような仮想通貨の特徴を頭に入れた上で、仮想通貨は取引をすることが重要です。
仮想通貨に纏わる税制について

続いて、『仮想通貨に税金は掛からないでしょ?』と思っている方も多いと思いますが、実際はしっかりと税金が課せられます。
仮想通貨は「雑所得」という扱いで、確定申告の際に他の所得と合計した金額に税が課せられます。所得に対しての最大課税率は45%で、地域にも異なりますが、大体住民税が10%課せられるため、最大55%の税金が掛かることになります。
例えば、仮想通貨で「億り人」と呼ばれる億単位で稼いでいる方は半分以上、税金で持っていかれてしまうのです。「自分はそこまで仮想通貨で儲けるわけないし」と思っている方も要注意です。先ほどもご説明した通り、仮想通貨は乱高下が激しいのが特徴です。
ふと気づいたときには想像しないくらい以上に大きな値動きがあり、自分が「億り人」になっているかもしれません。もし、そうなったときに仮想通貨を日本円に換金すると課税が課せられますので、事前にそのような税制度を認識しておくことは大切です。
仮想通貨の送金ミスの可能性

仮想通貨は、安いコストで素早く世界中の取引所やウォレットに送金できることが特徴の一つです。しかし、ここで注意しなければならいのが送金ミスです。
銀行の場合は、振込時に振込先の支店名や口座名義などを確認できたりすることから、送金ミスが起こる可能性はあまり高くはなく、また、振込を後から組み戻すこともできます。
一方で、仮想通貨の場合は銀行のように中央に管理者がいないため、間違ったアドレスに送信しても、取り消しをすることができません。
そのため、間違ったアドレスに送金手続きをしてしまうと、自分が所有していたコインが失われてしまう可能性もあります。そのため、仮想通貨の送金を行う際には、宛先のアドレスの入力ミスに十分注意する必要があります。
国や政府が規制をかける可能性がある

仮想通貨は国家の管理を受けない通貨のため、「仮想通貨は不正送金などに悪用される可能性が高い」と考える国家も存在します。
例えば、中国では2017年9月にICO(新規に仮想通貨を発行することで、ビットコイン(BTC)などの仮想通貨を集める形式の資金調達)が禁止されました。
これによって、中国で営業していた仮想通貨の取引所は、実質的な閉鎖に追い込まれました。このことが原因で「中国マネー」が多く入っていた一部の仮想通貨が大暴落しました。
ただし、この時は仮想通貨市場が上昇相場だったこともあってか、『安値でビットコイン(BTC)が買える』という人も殺到し、すぐに元値に戻りました。
なお、今のところ日本は中国のように全面的に仮想通貨を禁止してはいません。2017年4月に、日本では他国に先駆けて仮想通貨に関する法律の「仮想通貨法(改正資金決済法)」が制定され、法律的に仮想通貨を認めています。
仮想通貨が危険と思われた事件

2014年に、仮想通貨の取引所のマウントゴックスにて、顧客が保有する75万ビットコインの他、購入用の預り金も最大28億円消失してしまった事件が発生しました。
この事件が原因で『ビットコイン(BTC)は危険だ!』や『仮想通貨は危険だ!』というイメージが多くの方についたと考えられており、その記憶から今でも仮想通貨は危険と思っている方が多くいるようです。
しかし、2017年には仮想通貨に関する法律が制定され、金融庁が大規模な監査や規制を始めたことにより、現在の仮想通貨市場は、以前よりも健全で安全なものになりつつあります。
また、ビットコイン(BTC)をはじめとした仮想通貨が利用できる店舗やサービスも、世界中で増えきています。それだけ、世界各国の企業が仮想通貨の技術に注目をしているということでしょう。
仮想通貨は今後伸びる?リスクもあるが大きな可能性も

仮想通貨がニュースで取り上げられるときは悪い話題の場合が多いこともあってか、その情報ばかり見ていると『仮想通貨は危険なものなんだ』と誰もが思ってしまうと思います。
確かに、仮想通貨にはリスクはありますが、それは株やFXなどすべての取引で言えることですので、仮想通貨だけがずば抜けて危険ということは言い切れません。リスクはある反面、その可能性も大きいものとなっていることは確かです。
実際に、現状私たちの生活の中でも仮想通貨はどんどんと浸透してきています。日本でも、仮想通貨を使ったサービスや、仮想通貨を利用できる店舗などは以前よりも増えてきています。
例えば、ビックカメラやソフマップ、メガネスーパー、通販サイトなどでもビットコイン(BTC)などの仮想通貨の利用が可能になりました。
また、大手のメガバンクである三菱UFJ銀行が、仮想通貨のブロックチェーン技術を活用して独自に作り出した仮想通貨Coin(旧MUFGコイン)を、今後一般公開する予定ともなっています。
日本でも大手のメガバンクが仮想通貨を発行することで、今まで投機的な目的で利用されていた仮想通貨が、日常生活で使うためにもっと活用されることも予想されています。
仮想通貨の危険を回避する方法

仮想通貨にはリスクもあることは確かですので、リスクを最小限に抑えるように回避するための術を頭に入れておくことが大切です。
1. しっかりと情報収集をしてから仮想通貨投資に参入する
まず、SNSなどで『仮想通貨でこんなに儲かった!』や『今、仮想通貨を買わなければ分かれば損をする』といった意見をそのまま鵜呑みにして、仮想通貨投資に参入するのはリスクがあります。
中には信頼性の高い情報もありますが、一方で、投資の知識がない人をターゲットにした詐欺事件も過去に何度か起きています。
特に、「これは新しい仮想通貨で価値が保証される、絶対値上がりする、今買わなきゃ損!」などと言って宣伝しているような人が勧める仮想通貨には、手を出さない方が安心です。
SNSやインターネット、本や雑誌などを活用して、ある程度仮想通貨の情報を収集してから、仮想通貨への投資を始めるのが良いでしょう。
2. 最初は少しの金額から購入する

また、最初から大きな金額を購入すると、それなりのリスクも伴いますので、まずは少額ずつ購入することをオススメします。
Coincheckの販売所では500円から仮想通貨の購入が可能で、取り扱いの仮想通貨も11種類ありますので、少しずつ自分が気になった仮想通貨を購入することができます(2019年12月時点)。
3. ICOには注意する
仮想通貨には「ICO(Initial Coin Offering)」と呼ばれるものがあります。
これは、プロジェクトのためにオリジナルトークンを発行し、そのトークンを販売することによって、事業のための資金集めをすることです。
仮想通貨で起こる詐欺の多くはこの「ICO」によるものと言われています。仮想通貨を新規発行する企業はベンチャー企業などが多く、ベンチャー企業は設立から数年で姿を消してしまうことも珍しくありません。
すべてのICOが詐欺ということではありませんが、プロジェクトも技術を上手くいかずにプロジェクト自体が破綻してしまうことも珍しくありません。仮想通貨に対する知識が豊富でない場合、ICOの参加は控えておいた方が無難でしょう。
仮想通貨の危険性と将来性に関するまとめ

今回は、仮想通貨の危険性と将来性についてご紹介させてもらいました。
仮想通貨自体が怪しいものではないことはご理解いただけたかと思いますが、資産運用をするのであれば、少しでもリスクがないところに投資したいというのは誰もが思うことだと思います。
仮想通貨のリスクについてしっかりと理解して、慎重に投資を行えば安全な取引を行うことができるでしょう。これから、仮想通貨の取引を検討している方は、情報取集を欠かさずリスクを最小限に抑える対策を心がけておきましょう。
このコンテンツは会員のみが閲覧可能です。もしあなたが当サイトに登録したい場合は下記のフォームから登録してください。





